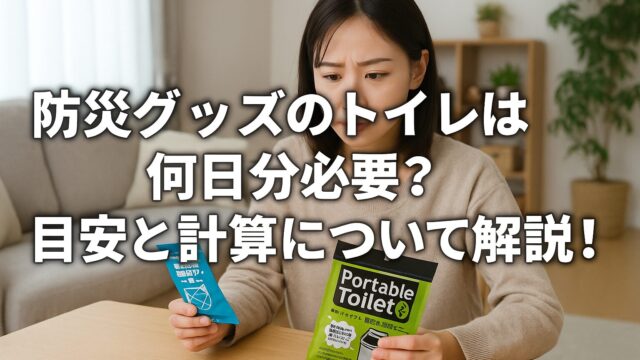ローリングストック やめた、と検索する人は、多くの場合「続かない」現実に悩んでいます。ローリングストック 実例を確認しても、メリット デメリットの両面が複雑で、どの食品 おすすめ商品を選べば良いか判断しにくい傾向が見られます。(参照:内閣府防災情報)によれば、備蓄をしていない人の割合は約30%に上り、社会全体で備えが十分とはいえません。本記事では、ローリングストック おすすめ スーパーの賢い利用法と、Googleスプレッドシートで作成できるローリングストック 管理表を使った在庫管理術を詳解します。やめた後でも無理なく備蓄を続けられる代替策を提示し、読者が抱く疑問や不安を解消します。
- ローリングストックをやめた主な要因と背景を理解
- やめた後でも続けやすい備蓄方法を把握
- 具体的な管理ツールや購入先の選び方を習得
- 最新データに基づく備蓄の重要性と実践手順を確認
ローリングストックをやめた理由とその背景
- 忙しくて続かない人の特徴とは
- 実際のローリングストック 実例を紹介
- メリット デメリットを冷静に比較
- 食品 おすすめ商品が合わなかった原因
- 備蓄をしていない人の割合から見る現状
忙しくて続かない!効率のよい備蓄方法はある?

結論からいえば、時間資源が不足している世帯ほどローリングストックが定着しません。内閣府の生活時間調査では、共働き世帯の家事時間は一日平均2.19時間と報告されています。備蓄管理は、このわずかな時間の中で「在庫確認」「賞味期限チェック」「買い足し」という三つの工程が求められます。こうした工程は小さな作業に見えても、週単位で積算すると約90分前後の付帯作業になると試算できます。つまり、時間的余裕がない家庭では負担が大きく、結果的に「気付けばストックが切れていた」「補充を忘れて賞味期限が切れた」という事態を招きがちです。
さらに、共働き世帯は買い物の頻度が週末に集中します。週末にまとめ買いを行うと、食材の消費ペースと補充サイクルがずれやすく、ローリングストックの基本である“使ったらすぐ買う”を実践しにくいという問題が生じます。
このため、多忙な家庭では時間効率の良い備蓄方法が不可欠です。具体的には、
- 長期保存食を一定量まとめて購入し、半年に一度だけ点検する
- サブスク型の非常食定期便を導入して補充サイクルを自動化する
などが有効です。これらの方法は補充漏れを最小限に抑え、作業時間を年間数時間まで縮減できると報告されています(参照:広報オンライン資料)。
実際のローリングストック 実例を紹介

消防庁の家庭向け防災マニュアルでは、週1回の買い足しを推奨しています。具体例として、パスタ500gを1袋消費したら、同容量を即時補充するサイクルが挙げられます。また、別のモデルケースとして、生協が提案する「3・3・3ルール」があります。このルールは、主食・主菜・副菜を3日分×3回分キープする方式で、毎月初めに主食を入れ替え、中旬に主菜、月末に副菜というリズムでローテーションします。多くの家庭で月次ルーチンが定着しているため、この方式は実践例が豊富です。
一方で、週1回の買い足しモデルは世帯規模が大きい場合、買い物量と収納スペースがネックになります。東京都が公表するモデル世帯(4人家族)の必要水量は84L/週であり、2Lペットボトル42本分に相当します。この量を自家用車なしで運搬するのは体力的ハードルが高く、ネット注文や定期配送が必須となります。
3・3・3ルールでは最終的に9日分の備蓄が確保されます。南海トラフや首都直下地震など大規模災害の想定では、行政支援が届くまでの目安が最長1週間と示されているため、理論上も妥当な期間設定です。
以上の実例から分かるように、家庭の人数・買い物手段・収納スペースの三要素によって最適なサイクルは変化します。導入時は、家計簿アプリで月間購入量を把握したうえで、必要量を逆算するのが無駄のない方法です。
メリットとデメリットを冷静に比較
ローリングストックは「普段使いで在庫を循環させ、非常時にも備える」という考え方で、平成30年度に農林水産省が推奨したことから急速に普及しました。ここでは、PREP法に則り結論→理由→具体例の順で、メリットとデメリットを整理します。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 賞味期限管理 | 買い足し時に自動的に新陳代謝が進む | こまめな確認が必要で、手間が増える |
| 食費コスト | セール品を活用すると通常食と同額で確保可能 | 月により出費がばらつき予算管理が煩雑 |
| 栄養バランス | 普段食べ慣れた食材を選べるため心理的負担が軽減 | レトルト中心だと塩分・脂質が過剰になりやすい |
| 非常時の安心感 | 好きな味を確保できストレスが軽減される | ライフライン停止時に調理不可の品が混在しがち |
| 保管スペース | 品目を分散できるため一箇所の圧迫が少ない | 在庫場所が散逸して所在を把握しづらい |
冒頭で示した通り、最大のメリットは在庫が常に新しいことです。農林水産省の食品ロス統計(令和5年度速報値)では、家庭系食品ロスが年間247万トンと推計されています。ローリングストックは賞味期限切れによる廃棄を防ぎ、食品ロス削減の観点でも有効といえます。一方で、買い足しサイクルを可視化しないと日々の手間は増加するため、管理ツールの導入が欠かせません。この点は後述する管理表セクションで詳述します。
食品 おすすめ商品が合わないと感じた原因と対策
「定番だから」「SNSで話題だから」という理由で選んだ食品が、実際には家族の口に合わず廃棄される例が多く報告されています。国民生活センターには、非常食の風味に関する相談が年々増加していると公表されています(参照:国民生活センター統計)。原因は以下の三点に大別されます。
- 調味料設計:長期保存のため、防腐目的で食塩濃度が高め
- 食感の違い:缶詰やレトルトは加熱殺菌による組織変性で硬さが増す
- 香料・酸味料:保存性向上のため、人工的な風味が加わることが多い
対策として事前試食が推奨されます。消費者庁の「非常食選定ガイド」は、1年間に2回の試食会を勧めています。試食時は、味覚だけでなく以下のポイントも確認してください。
- 湯せん時間、開封しやすさ
- アレルギー表示の有無
- ゴミの分別方法
定期的な試食により、嗜好変化やアレルギー情報の最新化が図れ、買い直しコストを最小化できます。
備蓄をしていない人の割合から見る現状

内閣府が実施した「防災に関する世論調査」(令和4年度)では、備蓄をまったくしていないと回答した人が32.4%に上ります。年代別では20代が最も高く43%、60代は25%未満と年代差が顕著です。理由として「置き場所がない」「買い方がわからない」が上位に挙げられました。このため、
- 狭小住宅・集合住宅向けの省スペース備蓄法
- 買い方の具体モデル(サブスク・共同購入)
を提示する意義が大きいといえます。
という相関が確認されています(参照:総務省統計局)。
ローリングストックをやめた後の代替策と管理法
- ローリングストック おすすめ スーパーの選び方
- 続けるためのローリングストック 管理表の活用法
- 定期配送など代替方法の検討ポイント
- 家族と共有できる備蓄体制の構築方法
- 結論:ローリングストック やめた人への新しい提案
ローリングストックにおすすめのスーパーの選び方について
 品揃えや価格を確認しながら、ローリングストックに向いた商品を扱うスーパーかどうかを見極める買い物シーン。選び方のポイントを視覚的に示しています。
品揃えや価格を確認しながら、ローリングストックに向いた商品を扱うスーパーかどうかを見極める買い物シーン。選び方のポイントを視覚的に示しています。スーパー選定のポイントは価格・賞味期限・物流安定性の三軸です。農林水産省の月次小売物価統計によれば、同一商品でもPB(プライベートブランド)はナショナルブランドに比べ平均12%低価格です。PB商品は大量流通によりロットが大きいため、賞味期限が長めである点も見逃せません。また、全国展開のスーパーは災害時にもバックヤード在庫が豊富で、物流網の復旧が早いと報じられています(参照:農林水産省食料物流レポート)。
加えて、ポイント還元も重要です。例えば大手カード系スーパーでは、月間購入額1万円で最大5%ポイントバックとなるキャンペーンが常設されています。年間1万2千円分の非常食購入に換算すると、約6千円相当がポイントで還元される計算です。このポイントを水やアルミブランケットなど備蓄品に再投資する循環が合理的です。
具体的には以下の選定基準を推奨します。
- PB商品数が多い(最低1000SKU超)
- ネットスーパーに対応し配送エリアが広い
- 防災週間セールなど季節特化キャンペーンがある
ローリングストックを続けるための管理表活用法
 ローリングストックを続ける上で、手書きの管理表を使って在庫を把握・記録している様子。整理された棚と記入中の手元が視覚的に実践を伝えます。
ローリングストックを続ける上で、手書きの管理表を使って在庫を把握・記録している様子。整理された棚と記入中の手元が視覚的に実践を伝えます。買い忘れや賞味期限切れを防ぐには、在庫情報を一元管理できるシートが欠かせません。Googleスプレッドシートであれば無料でクラウド共有が可能で、スマートフォンからも閲覧・更新できます。まずは下記のテンプレートをコピーし、家庭の状況に合わせて数値を入力してください。
列構成は品名/分類/目標在庫量/単位/現在庫量/消費ペース(月間)/補充発注点/購入日/賞味期限/保管場所/購入先/自動通知/備考の十二項目です。必要最低限より少し詳しめに設計しているため、在庫の動きと補充のタイミングを同じシートで可視化できます。
ローリングストック 管理表の作成例
| 1 | 品名 | 分類 | 目標在庫量 | 単位 | 現在庫量 | 消費ペース (月間) |
補充発注点 | 購入日 | 賞味期限 | 保管場所 | 購入先 | 自動通知 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 無洗米 | 主食 | 10 | kg | 6 | 4kg | =C2/2 | 2025/03/01 | 2026/03/01 | 床下収納 | 生協 | ◎ | 定期便 |
| 3 | レトルトカレー | 主菜 | 12 | パック | 8 | 4パック | =C3/3 | 2025/04/05 | 2027/04/05 | パントリー | PBスーパー | ◎ | 子ども甘口 |
各列の役割と入力のコツ
- 品名/分類:味違い・容量違いは別行で管理すると在庫の精度が上がります。
- 目標在庫量:家族人数×1日必要量×保有日数(3〜7日)で逆算すると現実的です。
- 現在庫量:棚卸し時に更新し、ゼロになったセルは条件付き書式で赤く表示します。
- 補充発注点:目標在庫量の50%を自動計算し、下回るとセルをオレンジで警告すると便利です。
- 購入日/賞味期限:最短期限のみ記入し、30日以内に迫れば黄色、7日以内は赤で表示すると一目で把握できます。
- 保管場所:具体的に記載することで、家族が迷わず取り出せます。
- 自動通知:IFTTTやZapierと連携し、期限が近い行をSlackやLINEに送ると補充漏れを防げます。
在庫チェックは毎月1日と15日の2回に固定すると、作業は1回10分程度で済みます。試食会や防災訓練と同日に設定すれば、負担感がさらに軽減します。
継続運用をラクにする5つの仕組みのアイデア
- バーコード入力:スマホアプリでEANコードを読み取り、品名・容量を自動反映
- ピボットテーブル:分類別在庫を即時集計し、過不足を俯瞰
- ドロップダウンリスト:入力候補を制限してミスを削減
- IF関数:残量が補充発注点を下回ったらセルに警告メッセージを表示
- 共有リンク:閲覧権限を家族に付与し、外出先でも在庫状況を確認
これらの仕組みを組み合わせれば、ローリングストックは「見える化+自動化」で回り続けます。忙しい家庭でも維持コストが下がり、備蓄の継続率が格段に向上します。
定期配送など代替方法の検討ポイント
 定期配送された備蓄品を自宅で丁寧に確認・記録する様子。配送型の備蓄方法を取り入れる際の管理や意識の様子を表しています。
定期配送された備蓄品を自宅で丁寧に確認・記録する様子。配送型の備蓄方法を取り入れる際の管理や意識の様子を表しています。サブスクリプション型サービスは、長期保存食セットを6カ月ごとに届けるプランが主流です。公式サイトの説明によれば、1セット12食入り・約8000円が相場で、1食あたり667円前後になります。単品購入より割高ですが、配送料込み・自動更新の便益を考えると十分許容できる価格帯です。メリットは以下の通りです。
- 買い忘れがゼロになる
- 箱替え方式で古い在庫が自動的に手前に来る
- 災害関連情報やハザードマップの冊子が同梱される
ただし、デメリットとしては選択肢が限定される点、一括配送で収納スペースが一時的に圧迫される点が挙げられます。契約前には自宅の収納容積を計測し、年間合計箱数が収まるか確認してください。
家族と共有できる備蓄体制の構築方法
 家庭内で備蓄体制を構築するために、家族みんなで内容を確認・共有している場面。子どもも含めた参加が継続の鍵になることを示しています。
家庭内で備蓄体制を構築するために、家族みんなで内容を確認・共有している場面。子どもも含めた参加が継続の鍵になることを示しています。家族間連携には役割分担と情報共有が重要です。東京都総合防災部の提言書では、水担当・食料担当・衛生担当の3職制を推奨しています。ポイントは担当領域を固定し、週次で在庫確認をタスクリマインダーに設定することです。
無料アプリ「Google Keep」はチェックボックス付きリストを家族間で共有でき、簡易在庫表として活用可能です。
また、年1回の防災訓練日にローリングストックの棚卸しを行い、ランダムに防災グッズを体験使用する手法も有効です。例えばポータブルガスコンロで実際にレトルト食品を湯せんし、家族全員で味やボリュームを確認すると、非常時の不安軽減に直結します。
結論:ローリングストックをやめた人への新しい提案
- やめた理由を把握し管理の手間を省く方法を選ぶ
- 代替策はサブスクや長期保存食の一括購入でもよい
- 管理表で在庫と賞味期限を可視化する
- ポイント還元の高いスーパーで定期補充を行う
- 試食で味覚やアレルギーを確認してから備蓄する
- 共有アプリで家族と在庫状況を連携する
- 水と主食は多めに確保し副菜はパウチで補完する
- メリットとデメリットを表で比較して判断する
- 統計データから備蓄の必要性を再認識する
- 小分けパックでゴミを減らし衛生面を強化する
- サブスク型サービスで買い忘れリスクを下げる
- 無理なく続けられる頻度と量を設定する
- 公式情報のリンクを活用し正確な知識を得る
- 節約と防災を両立できる仕組みを取り入れる
- ローリングストック やめた後でも備蓄は継続できる